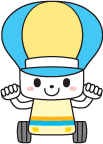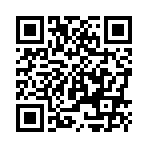バス停#62 佐賀城下長崎街道西の入り口 「高橋」
2016年07月20日
今日のバス停は「高橋」

ここを出発し、以前から気になっていたあるスポットまで歩いてみます。

バス停名の由来はこの橋の名前から
「高橋」は佐賀市嘉瀬町の扇町と八戸(旧八戸町)を分ける本庄江川に架かる橋で、バス路線の国道207号線に架かる橋が「(新)高橋」、その約50m北の長崎街道筋に架かっている橋が復元された「(旧)高橋」です。
【18】徳万・久保田線、【27】嘉瀬新町・久保田線のバス車内からも、この「(旧)高橋」の姿を見ることができます。

高橋は、慶長年間、佐賀城下町建設の時に架設されたと考えられています。
佐賀城下長崎街道の西の入り口にあたる場所で、江戸時代まで高橋周辺は市として栄え、瓦屋、かまぼこ製造屋、元結紙製造屋などがあり賑わっていました。
この高橋から東へ長崎街道沿いに高橋宿があり、その先が鍵の手に折れ曲がり八戸宿へつながっていました。

この鍵の手のところに番所があったそうです。
もう1つのスポットはこの先

案内表示から左折し

細い道を約200m進んだところにあります

佐賀の七賢人「江藤新平の誕生地」
建物は残っていませんがこの案内板が立っています。

 1834年(天保5年)2月9日ここで生まれた江藤新平は、11歳の時に藩校弘道館に入学し、19歳の時には副島種臣の兄、枝吉神陽(えだよししんよう)のもとで学びました。明治新政府の初代司法卿(しほうきょう)となり多くの業績を残しましたが、「佐賀戦争」を起こし敗北、1874年(明治7年)に処刑されました。
1834年(天保5年)2月9日ここで生まれた江藤新平は、11歳の時に藩校弘道館に入学し、19歳の時には副島種臣の兄、枝吉神陽(えだよししんよう)のもとで学びました。明治新政府の初代司法卿(しほうきょう)となり多くの業績を残しましたが、「佐賀戦争」を起こし敗北、1874年(明治7年)に処刑されました。
出典:日新校区史跡ガイドマップ
今日は高橋バス停周辺を歩きましたが、長崎街道沿いには多くの歴史遺産が残っています。バス路線は長崎街道とほぼ平行して通っているので、長崎街道の散策にはバスが大変便利です。
歴史に興味のある方は、夏休みにバスで長崎街道の歴史探訪をしてみてはいかがですか。



P.S.
帰りにふと街道に目を向けると、ここにも丸型ポストが残っていました。

意外とあるんですね

高橋と言えばここも外せません。 バス停正面の「高橋餅本舗 福屋」さん
もちろん大福買って帰りました
続きを読む
ここを出発し、以前から気になっていたあるスポットまで歩いてみます。

バス停名の由来はこの橋の名前から
「高橋」は佐賀市嘉瀬町の扇町と八戸(旧八戸町)を分ける本庄江川に架かる橋で、バス路線の国道207号線に架かる橋が「(新)高橋」、その約50m北の長崎街道筋に架かっている橋が復元された「(旧)高橋」です。
【18】徳万・久保田線、【27】嘉瀬新町・久保田線のバス車内からも、この「(旧)高橋」の姿を見ることができます。
高橋は、慶長年間、佐賀城下町建設の時に架設されたと考えられています。
佐賀城下長崎街道の西の入り口にあたる場所で、江戸時代まで高橋周辺は市として栄え、瓦屋、かまぼこ製造屋、元結紙製造屋などがあり賑わっていました。
この高橋から東へ長崎街道沿いに高橋宿があり、その先が鍵の手に折れ曲がり八戸宿へつながっていました。
この鍵の手のところに番所があったそうです。
もう1つのスポットはこの先

案内表示から左折し

細い道を約200m進んだところにあります

佐賀の七賢人「江藤新平の誕生地」
建物は残っていませんがこの案内板が立っています。
 1834年(天保5年)2月9日ここで生まれた江藤新平は、11歳の時に藩校弘道館に入学し、19歳の時には副島種臣の兄、枝吉神陽(えだよししんよう)のもとで学びました。明治新政府の初代司法卿(しほうきょう)となり多くの業績を残しましたが、「佐賀戦争」を起こし敗北、1874年(明治7年)に処刑されました。
1834年(天保5年)2月9日ここで生まれた江藤新平は、11歳の時に藩校弘道館に入学し、19歳の時には副島種臣の兄、枝吉神陽(えだよししんよう)のもとで学びました。明治新政府の初代司法卿(しほうきょう)となり多くの業績を残しましたが、「佐賀戦争」を起こし敗北、1874年(明治7年)に処刑されました。出典:日新校区史跡ガイドマップ
今日は高橋バス停周辺を歩きましたが、長崎街道沿いには多くの歴史遺産が残っています。バス路線は長崎街道とほぼ平行して通っているので、長崎街道の散策にはバスが大変便利です。
歴史に興味のある方は、夏休みにバスで長崎街道の歴史探訪をしてみてはいかがですか。




P.S.
帰りにふと街道に目を向けると、ここにも丸型ポストが残っていました。


意外とあるんですね


高橋と言えばここも外せません。 バス停正面の「高橋餅本舗 福屋」さん
もちろん大福買って帰りました

続きを読む